DX推進の基盤としてクラウドはかかせないものとなっており、中でもAWS、Microsoft Azure、Google Cloudは三大クラウドとしてシェアを奪い合っています。今回は各社の現状とAI利用の方向性で垣間見える戦略について考察してみました。後半部分は完全に個人の推測でしかありませんが、参考になれば幸いです。
各社のシェア:AWS>Azure>Google Cloud
まずは現段階でのシェアを見てみましょう。

Synergy Research Groupの調査結果によると、AWS・Azure・Google Cloudの順番のようです。
これら三社で全体の約6割ほどを押さえていますが、割合を考えるとGoogleが若干引けを取ってしまっているような状況です。GoogleはAmazonとMicrosoftを2023年に超えるよう強いられているとのことですが、このペースだとちょっと厳しそうな予感が…大丈夫でしょうか。Azureはここ数年でものすごく勢いを伸ばしていますね。
ちなみに日本に限定するとAzureとGCPの間にNTTと富士通が入るそう。
そもそも選ばれている理由
オンプレと比較したクラウドの良さはすっとばし、各社ならではの優位性を簡単に述べてみます。
AWSは”ユーザーファースト”

Amazonは2006年にクラウド事業に参入。そこからあっという間にシェアを獲得し、クラウド市場のリーダーとなりました。誰もクラウドに注目していない時期から投資をしていく先見の明もさることながら、評価されている理由は「ユーザーファースト」という点にありそうです。
その一つとして、値下げの回数です。AWSサービス開始からなんと129回も値下げをしているそうです(2022年12月時点)。最新技術を常に取り入れ続け、AWSサイドのコストを低下させその恩恵をユーザーに還元しているとのこと…SaaSビジネスだとある程度ユーザーを獲得できた段階で値上げをするというのはよくある手法ですが、常に値下げをし続ける姿勢があるとユーザーとしては非常にありがたいですね。※昨今の円安で円ベースでの料金は増えていますが、AWSの単価自体は値下げ傾向の模様です。
初期投資不要も利点の一つかとは思いますが、ほかのクラウドでも定額のクレジットを付与したりしているのでこれは無視しました。
Azureは使用率の高いツールとの親和性が高い

AzureはMicrosoftが開発しているため、Officeツールとの連携力の高さが魅力の一つとなっています。PCをOS別にみたシェアでもWindowsが7割を占めているので、普段の業務ツールから入り込みやすさがありそうですね。また、Web開発では最早必須となったVSCodeも簡単に連携ができることも魅力の高さです。拡張機能を用いればVSCodeでコーディングして即座にデプロイすることも可能のようで…開発者の視点だと作業工数が下がるのは非常に嬉しいのではないでしょうか。
また、セキュリティの高さという点でも他のクラウドよりも評価を受けている模様です。Microsoftはセキュリティへの投資を惜しまず実施していますし、これまでのノウハウをうまく生かしているのでしょう。
Google Cloudはデータ分析で優位性を持っている。

データ分析に必要なツールは三社とも揃っていますが、中でもGoogle CloudのBigQueryは分析において頭一つ抜けている印象です。BigQueryの利点はまず圧倒的計算速度の高さです。テラバイト級のデータに対しても高速で前処理を実施できます。
Google製品と簡単に連携できることも強みです。アクセス解析ツールであるGoogle Analytics(GA)はログデータの出力をBigQueryに簡単にできるようになっています。※現状ではBigQueryにしか出力ができないため、GAデータの分析をするならBigQueryを使用せざるを得ないという形ではありますが…
同じGoogle Cloud の製品であるVertexAIを用いることでBigQueryで前処理したデータを用いてモデル作成もできますし、BigQueryにも機械学習モデルを作成する機能(BigQuery ML)が備わっていますので、蓄積したデータからAIによる予測を行うことも容易にできちゃいます。
データウェアハウスといえばBigQueryと即答している人も多いです。ただ。AWSとの連携力は微妙(当然っちゃ当然)なので、まだAWSを利用していかつデータ分析に力を入れたいのであればクラウドとしてGoogle Cloudを利用するという方向になるかと思います。
※僕もBigQueryを使っていましたが非常に使いやすいプロダクトだなと思っています。
AIを利用した各社の戦略?
ここまで各クラウドが選ばれている理由について述べてみました。ここからは本題の戦略考察について述べてみます。
生成AI利用でAzureはAWSに食らいつこうとしている?
僕個人の推測では「OpenAIと手を組むことによってAmazonとGoogleどちらからもシェアを奪い取ろうとしているのではないか」と考えています。
MicrosoftはOpenAIに多額の投資を複数回しています。2023年の年始にもさらに投資を行い、AI技術を世の中へ共有する取り組みを続けていくと発表しています。
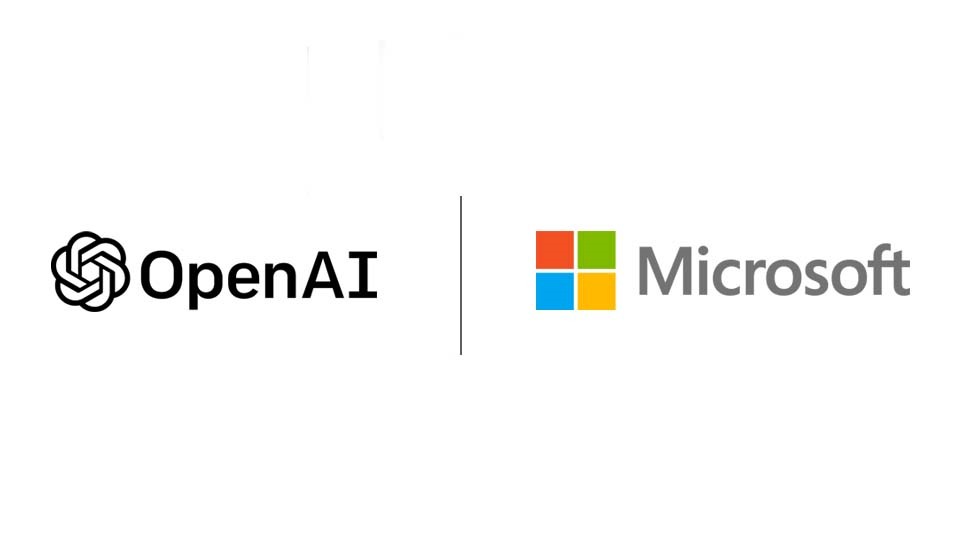
その宣言通り、自社プロダクトへの組み込みも積極的に開始しています。最近だとBingがAIチャット化したり、AzureではGPT3.5-turboのファインチューニングをサポートしたりなど…ここ数か月の出来事とは思えないほどリリースを連発しています。
これらの取り組みによって検索エンジン領域では打倒Googleに、クラウド領域では打倒Amazonを目的としているのではないか?と勝手に推測しています。2023年2月末時点でBingのアプリDL数はすでに2022年の数値を上回ったとのこと。chatGPTの効果はえげつないですね…生成AI一つで検索エンジンとクラウドどちらもトップをとれるかもしれない、となったらこの積極性も理解できるような気がします。
Googleも生成AIをサポートすると発表
Googleもこの動きに追随し、3月14日に生成AIをGoogle Cloudで提供すると発表しました。

上記リリースから一部を抜粋すると
- VertexAIで生成AIをサポート。
- 様々なユースケース(コンテンツ生成、チャット、要約、分類などにすぐに対応できる。
- Google の最新基盤モデルから選択: オプションとして、Google Research と DeepMind が発明したモデルや、テキスト、画像、動画、コード、音声などさまざまなデータ形式をサポートします。
- Generative AI App Builderをリリース
- 開発者はボット、チャットアプリ、デジタル アシスタント、カスタム検索エンジンなどの gen app の作成を限られた専門知識で迅速に開始することが可能です。
- 情報の提供だけでなく、取引も可能に: デジタル アシスタントやボットは、単にコンテンツを提供するだけでなく、購買システムやプロビジョニング システムに接続し、状況に応じて顧客との会話を人間のエージェントにエスカレートさせることができます。
3月18日時点では利用できるのはテストユーザーのみで、一般利用開始の期日は明記されていませんでした。同時期にGPT4対応のchatGPTもリリースされていたのでそれに比べるとちょっと見劣りするような気はしますが、Googleも十八番のAI技術を積極的に自身のクラウドに取り入れる姿勢が見えますね。BingのAIチャット化にGoogleは遅れをとったと言われていますから、やはりこれ以上差を広げるわけにはいかないという危機感もあるのではないでしょうか。
AWSは?
ここまでMicrosoftとGoogleの動きに関して記載してきましたが、Amazonはどうでしょうか?

2月にHugging Faceと連携して生成AIを利用しやすくすることを発表していました。
昨年話題になったStable DiffusionもAWSで利用できるようになっていますし、AWSもこの流れにしっかりと追随しています。シェアNo.1の座に胡坐をかくことなく変化に対応していることがわかりますね。この記事を書いて初めて知ったのですが、AWSはHugging Faceとの提携を2021年に締結していたみたいです。リリースの速さからも「自分たちもこの流れに対応していますよ」という意思が伝わってきます。
まとめ
長々と書きましたが、これまでの動きと各社の狙い(僕の考察)を書くと下記のような感じになるかなと思います。
- MicrosoftはOpenAIと連携することでクラウドのシェアをひっくり返したい。
- Googleも負けじと生成AIのサポートを発表。これ以上クラウド市場の差を広げたくない。
- AmazonもHugging Faceと連携を強化することを発表し、この流れに対応している姿勢を見せている。
Google、Amazomいずれも生成AIを取り入れることを発表し、Microsoftの猛追に劣らないようしていました。生成AI関連のニュースはまだまだ勢いが止まりませんし、今後の動きにも注目ですね。
追記(10/15)
AWSがAmazon Bedrockという新しい生成AIプラットフォームを4月にリリースし、東京リージョンでの利用も10月にGAとなりました。こちらはサーバーレスでAmazonが提供する基盤モデルを利用することができ、他のAWSサービスとの統合・デプロイが可能です。GCPのGenerative AI App Builderに近いものでしょうか?やはり各社の動向は見逃せないですね

最後まで読んでくださりありがとうございました!



コメント